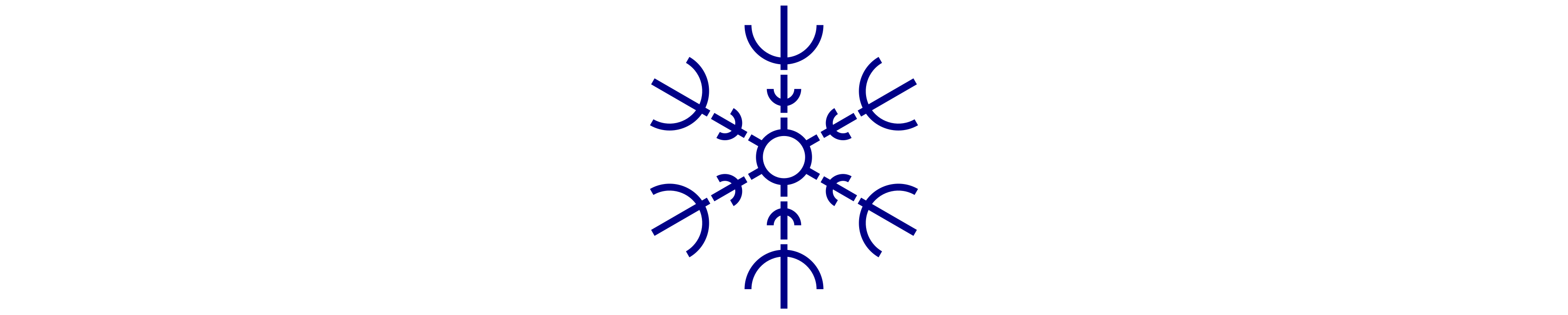あるとき、ひとりの男が旅をしていた。男は道に迷い、どこに向かって歩いて行けばよいか分からなくなった。暫く歩き続けてようやく一軒の農場にたどり着いたが、そこはまったく知らないところであった。男は母屋のドアを叩いた。中年を過ぎたひとりの女が戸口まで出てきて、中に入るよう促し、男はそれに応じた。母屋は農場の建物のなかでも立派な方で、居心地がよかった。女が案内した居間の前には、若くて美しい二人の娘がいた。この娘たちとその母である中年を過ぎたひとりの女を除いて、男が見た人間は他に誰もいなかった。男はよくもてなされ、食べ物と飲み物をもらい、それから寝床に案内された。どちらかの娘と寝てもよいか、と男が訊ねたところ、それは聞き入れられた。そうして男と娘は横になる。男が娘の方を向こうとしたときのことだ。娘がいたところに誰の身体もないことに気づいた。男が手を伸ばせば娘に触れる感触があるのだが、手の間には何もない。さっきまで娘はベッドの上で大人しくしていて、男はその姿をずっと見ていたはずなのだが。いったいこれはどういうことかと男は娘に訊ねる。驚いてはいけません、と娘は答え、さらに「私は肉体のない存在なのです」と続けた。「遠い昔、悪魔が天界に混乱をもたらしたとき、悪魔とそれに付き従って戦ったものはすべて、かの冥界へと追放されました。悪魔を讃えるものもいましたが、そうしたものはみんな天界から追い出されました。悪魔に与することも対することもなく、どちらの陣営にも入らなかったものは、下界の地上へ落とされて、丘や山や岩のなかに住むように命じられ、今では妖精や隠され人と呼ばれています。彼らは自分たち以外には何者とも一緒に住むことが出来ません。善行と悪行のどちらをすることもできますが、するとなればどちらも徹底的に行います。彼らは貴方のような人間と同じ肉体を持っていませんが、自らが望む時には貴方たちに姿を見せることができるのです。私は、その隠された存在から生まれた身ですから、貴方はもうこれ以上のものを私から得ることは出来ません」。男はこれを受け入れて、その後、娘が釈明したことを人々に語った。
(„Uppruni álfa“ 1862. Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. I. bindi. Safnað hefur Jón Árnason. Leipzig: J.C.Hinrichs. Bls. 5-6.)