こんな話がある。あるとき、ひとりの男がよくするように漁に出たのだが、陸に戻ろうとしたとき、南から向かい風が吹いてきて、陸からどんどん遠く遠くへと流されていった。これは沖まで流されたに違いない。男が狼狽えだしたのは、遠くへ流されるほどに辺りがどんどん暗く暗くなっていったからで、やがて霧と暗さのために殆ど何も見えなくなった。しばらくして陸地に行きつくと、男は舟をしっかり繋ぎ止めて陸に降り立った。浜辺を掬ってみたが、何も見えなかったがために、そこの砂利は灰と炭でしかなかった。嫌な感じがし始めたが、男は北へ向かって進んでいった。道は下の方につづく急こう配で、真っ暗闇だった。かくして男は長く長いあいだ盲のままに歩きつづいき、すると、何か赤いものがぼんやり見えてきた。その鈍い光の方へ歩いてゆくと、向こう側が見通せないほど大きな焚き火に行きついた。男はひどく驚いた。その大火のなかには生きている何かが、蚊か屑のようにうじゃうじゃ蠢いていたのだ。それに焚き火の前には恐ろしい巨人が凄まじい鉄の鉤がついた棒を手にして立っていて、生きているものが何も外に出てこないように、火を突っついたり、辺りを掃いたりしていた。けれど羽虫のようなものが一匹、男のいるところまで飛び出てきた。男はそいつに名前と目の前のこれは一体何なのかと訊いた。すると羽虫は、男が見ている焚き火は地獄であり、あの巨人こそが悪魔であって、火のなかで蠢いているのは地獄に落ちた魂たちで、自分もそのうちのひとつなのだが、運良く逃れらたみたいだ、と言う。しかし羽虫が話し終わったとき、例の巨人がひとつ足りないことに気がついた―というのも、その悪魔が羽虫の面倒をみていたのだ―そしてその魂がどこにいるかを見てとると、鉄の鉤でぐいと掴んで放り投げ、羽虫は長い軌跡を描いて大火の真ん中にくべられた。男は怖くなって脱兎のごとく逃げだしたが、上の方への道は急こう配で、それはそれは長い道のりだった。けれど少しずつ少しずつ辺りが明るくなってきた。男は来た道をそのまま辿ったのだ。
人を恨みに思うがゆえに、どいつもこいつも、あれもこれも北へ下へ行ってしまえ、と言われるが、それは、この旅物語からそこが地獄であると知られているからであろう。この話の信憑性は、『受難聖歌』の一節によって高められているようだ。「焚き火に魂たちをくべるべく、悪魔がそこで待ちわびる」[1]原題は、Passíusálmar。牧師であり、アイスランド最高の聖歌詩人とされるハトルグリムル・ピエトゥルソン(Hallgrímur … Continue reading
ヨウン・アウルトゥナソン[2]ヨウン・アウルトゥナソン(Jón … Continue reading収集―ボルズエイリ村のピエトゥル・エフゲルトゥからの話
(„Farðu norður og niður.“ 1864. Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. II. bindi. Safnað hefur Jón Árnason. Leipzig: J.C.Hinrichs. Bls. 518.)
脚注
| ↑1 | 原題は、Passíusálmar。牧師であり、アイスランド最高の聖歌詩人とされるハトルグリムル・ピエトゥルソン(Hallgrímur Pétursson)(1614年―1674年)の代表作である長篇叙事詩のこと。イエス・キリストの受難の物語が計50の聖歌で綴られている。『受難聖歌』の第4歌20節には、「Djöfullinn bíður búinn þar, í bálið vill draga sálirnar.」とあるが、この民話における引用では、悪魔を意味する言葉が、「djöfull」でなく「andskoti」に定冠詞がついた「andskotinn」となっている。この一節においては、どちらの語でも同じ意味だが、「djöfull」は語源を古ギリシャ語の「διάβολος(diábolos)」に遡れる借用語であるのに対し、「andskoti」は「反して、対して(and-)投擲する、撃つ(skjóta)」を意味し、元々は、「敵対者」、「攻撃者」、「襲撃者」を指す語だと思われる。 |
|---|---|
| ↑2 | ヨウン・アウルトゥナソン(Jón Árnason)(1819年―1888年)は、アイスランド民話の収集家であり、アイスランド国立図書館の初代館長にして、現在のアイスランド国立博物館の前身であるアイスランド古物収集館の初代館長。童話「白雪姫」のアイスランド語訳者であるマグヌス・グリムスソン(Magnús Grímsson)(1825年―1860年)と協力し、1852年に『アイスランドのお伽噺(Íslenzk æfintýri)』を出版。マグヌスは1860年に死去したが、ヨウンは民話の収集をつづけ、1862年―1864年に2巻本の『アイスランドの民話とお伽噺(Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri)』を出版した。 |
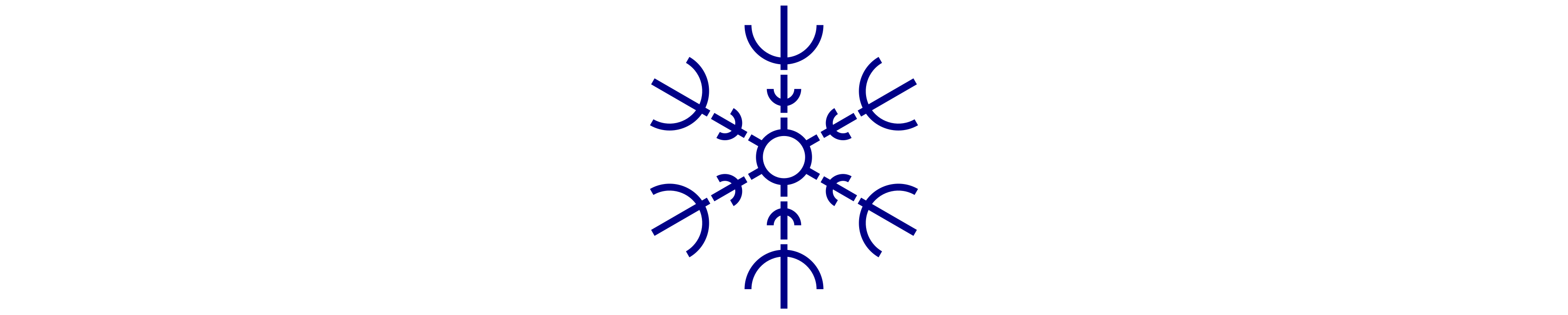
 (レイキャヴィーク市立図書館グロウヴィン館の1階にある彫刻作品)
(レイキャヴィーク市立図書館グロウヴィン館の1階にある彫刻作品)