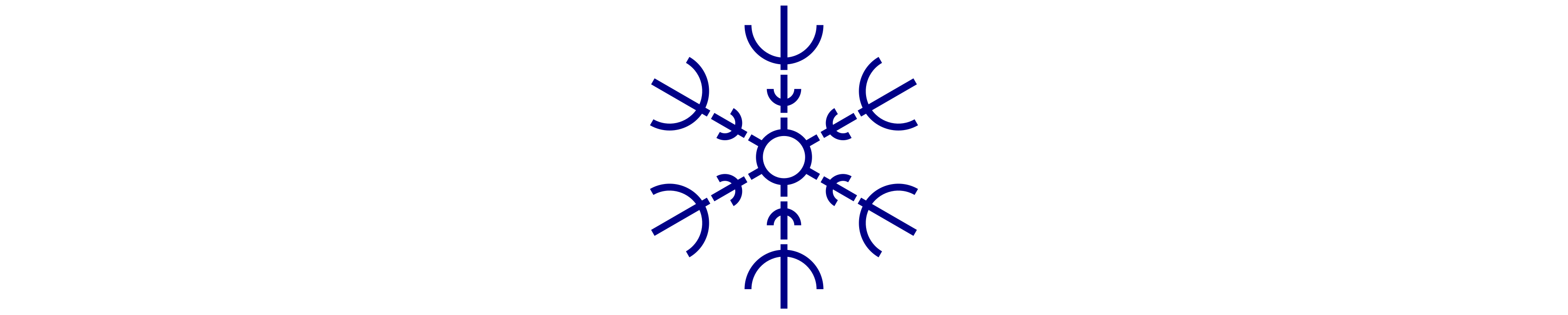遥か昔、海の向こうに、スヴァルティ・スコウリという学校が存在した。人々はそこで魔術を習得し、古代の叡智を蓄えた。どんなところだったのかといえば、ひどく頑丈な造りをした地下の建屋で、窓はひとつもなく、そのため屋内はいつも真っ暗闇だった。教師はおらず、人々は暗闇でも読める火のように赫い文字で書かれた本からすべてを学んだ。そこにいる間は外気に触れることも陽の光を見ることも決してなく、すべてを学び終えるまでには冬を三つから七つは越さねばならなかった。そこでは毎日、毛に覆われた灰色の手がひとつ、壁の辺りに現れて生徒に食事を渡していた。スヴァルティ・スコウリを運営するものは、毎年卒業する者たちのなかで最後に校舎から出ていく者を自分のものにできるという権利を持っていた。悪魔が学校を運営していることは誰もが知っていたため、最後に歩いて出ていくことを、そうできる者は誰であれ、避けたがった。
あるとき、スヴァルティ・スコウリに三人のアイスランド人がいた。賢者サイムンドゥルと、アウルトゥニの息子カウルヴル、それに、エルドヤウルトゥンかエイナルの息子で、のちにスリエットゥフリーズ坂のフェットル村で牧師になるハウルフダウンだ。彼らは同じときに学校から出ていかなければならなかったのだが、サイムンドゥルが最後に出て行くことを申し出た。残りの二人は安堵した。サイムンドゥルは、ボタンを留めることも袖に腕を通すこともせずに大きな外套を肩に引っ掛けた。学校の外へは上り階段が続いていた。サイムンドゥルが階段に足をかけたまさにそのとき、彼の外套を悪魔が掴んで言った。「お前をもらう」。その瞬間、サイムンドゥルは外套を投げ捨てて走り出した。悪魔の手が捕らえられたのは一枚の外套だけだった。鉄の扉が蝶番のところで唸りを上げ、サイムンドゥルの踵が通ったところで勢いよく閉まった。彼は踵の骨を傷めてしまった。このときサイムンドゥルは「踵近くで扉が閉まった」と言い――この発言は、のちに諺になった。こうして賢者サイムンドゥルは仲間と共にスヴァルティ・スコウリから去っていった。
ちなみに、賢者サイムンドゥルが階段を上がってスヴァルティ・スコウリのドアから出てこようとしたとき、彼の向かう先から陽光が射して影が壁に映ったのだ、と言う人もいる。悪魔がサイムンドゥルを捕らえようとしたまさにそのとき「私は最後じゃない。後ろのあいつが見えないのか?」と彼は言った 、と。それで人がいると思った悪魔はその影へと手を伸ばしていったが、サイムンドゥル自身は逃げ出して、彼の踵が通ったところで鉄の扉が勢いよく閉まった。だが、悪魔が捕えた影を決して手放さないがために、このこと以来、サイムンドゥルはいつでも影なしなのであった。*1
注。それぞれの時代における最大の博学者とされていた二人のアイスランド人をスヴァルティ・スコウリで同級とするため、賢者サイムンドゥルとフェットル村のハウルフダウンの間にあるはずの時代の大きな隔たりを、アイスランド人の想像力は飛び越している。サイムンドゥルが没するのは先述(「サイムンドゥルの灯台」の脚注を参照[1]原書に「サイムンドゥルの灯台(Viti Sæmundar)」という民話や項目は見当たらない。1954−1961年にかけて増補出版された『Íslenzkar þjóðsögur og … Continue reading)に拠ると1133年だが、ハウルフダウンの方は、後に述べるように1598年頃である。
*1 マウラー博士『Isländische Volkssagen』(Leipzip、1860)120-121頁、および『Íslenzk æfintýri』(Reykjavík、1852)33-35頁を参照。
(„Svarti-skóli.“ 1862. Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. I. bindi. Safnað hefur Jón Árnason. Leipzig: J.C.Hinrichs. Bls. 490-491.)
本文中の*1は原註であり、訳註は脚注にて示した。
脚注
| ↑1 | 原書に「サイムンドゥルの灯台(Viti Sæmundar)」という民話や項目は見当たらない。1954−1961年にかけて増補出版された『Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri』では、丸括弧の部分がすべて三点リーダに置き換えられて「先述の…に拠ると」となっている。参照:„Svartiskóli.“ 1954. Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. I. bindi. Nýtt safn. Safnað hefur Jón Árnason. Árni Böðvarsson og BjarniVilhjálmsson önnuðust útgáfuna. Reykjavík: Þjóðsaga. Bls. 475-476. |
|---|