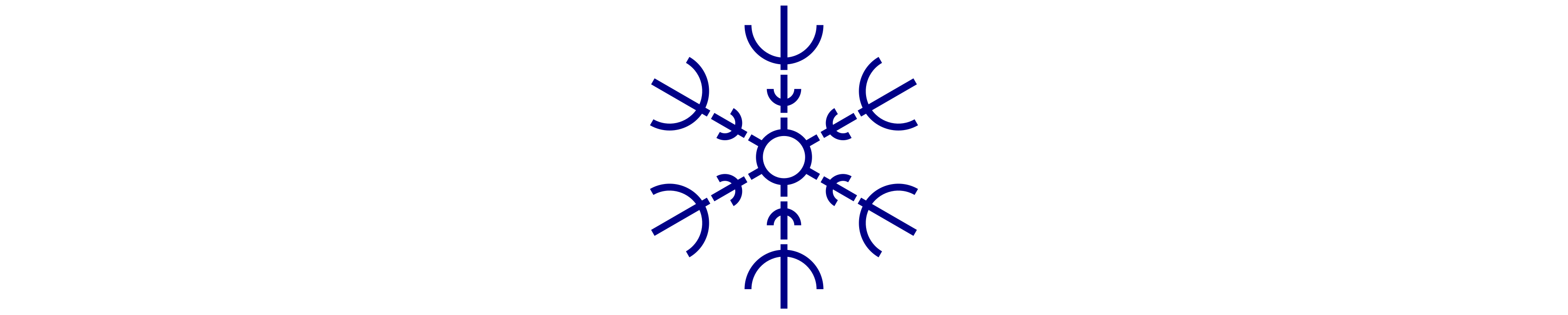グズヨウン・ラグナル・ヨウナソン著『他面』(2018年、Sæmundur)
書名(原語):Hin hliðin: Hinsegin leiftur- og örsögur
書名(仮):他面――クィア掌編小説
著者名(原語):Guðjón Ragnar Jónasson
著者名(仮):グズヨウン・ラグナル・ヨウナソン
原語:アイスランド語
出版年:2018年
版元:Sæmundur
ページ数:95
(https://www.forlagid.is/vara/hin-hlidin/)
以下は、『他面――クィア掌編小説』の著者グズヨウン・ラグナル・ヨウナソンと出版社Sæmundurの許可を得て公開する幾つかの仮訳である。今のところ具体的な翻訳や出版の話はないが、これを機に興味を持った方や出版社は、翻訳者(記事投稿者)にご連絡いただければ幸いである。
きみからの贈り物はよいものだが
レイキャヴィーク・プライド初年の仕事に関わることは、本当に喜ばしく、創造的でもあった。私の仕事は予算と出店の管理だった。どれだけのものが売れるかを見ているのは確かに楽しかったし、イベントの資金調達は上手くいっていたのだが、何より嬉しかったのは、人々がとても好意的に私たちを受け入れてくれたことだ。そうした人々の反応は、誰もがレイキャヴィーク・プライドのグッズを買って支援してくれたことに表れている。社会からの賛同と支援が得られたことは、レインボーフラッグを振っている親子の姿から明らかだった。他の場所とは違い、参加者の手に酒が見られないレイキャヴィークのプライド・フェスティバルは、親子のお祭りだったのだ。ベルグソウルスクヴォホトゥルのニャールに向けてフリーザルエンディのグンナルが言った言葉が、私の心を掴んで離さない。「あなたからの贈り物はありがたいが、あなたやご子息たちとの友情の方が、私には価値がある」
(„Góðar eru gjafir þínar.“ Bls. 88.)
3本で1000クローナの旗
振り返れば、レイキャヴィーク・プライドへの参加は楽しいものであったし、何より人間として成熟する機会を得た。意見の不一致はあったものの、初期のレイキャヴィーク・プライドのために尽力した面々は毎週集まって多くのことを話し合ったものだ。その場には草の根精神が満ち満ちていたが、資金繰りは絶えず頭痛の種だった。20世紀から21世紀に変わる頃は、広告しようと私たちのところに列をなす企業の姿はなかったのだ。そのため、信頼できる後援者を得ることが肝心で、支えてくれたのは殆どゲイ・コミュニティに属する人たちであった。だが、保険会社や銀行がレイキャヴィーク・プライドに惜しみない援助をするようになるまで長くはかからなかった。
ロイガヴェーグル通りの小売店主や個人も重要な役割を担っていた。彼らによる物販は盛況で、大量のTシャツや紙手旗は飛ぶように売れた。あれほどまでに多くの道行く人によって私たちの取り組みが熱心に支援されたことには、おかしなことかもしれないが、驚きを隠せなかった。祭りの初年には500クローナの手旗が500本も売れたことを受け、イベントの代表者のひとりは子どもの多い家族のための商品を用意した。3本で1000クローナ。翌年のイベントでは1000本の旗が売れ、さらにその翌年には2000本の旗が売られるだろうと予想された。しかし期待の年には土砂降りの雨が降ったことで、紙手旗は文字通り流れ去っていった。けれども何が売られるかはまったく問題ではなかったようで、その年もすべてのものが売り尽くされた。物を売る人のなかには芸術家や政治家もいて、はじめの一度を除けば、移動販売車両で商品を売ることを頼む必要はなかった。あるレイキャヴィーク市議会議員は、毎年家族と一緒にやって来て大きな売上を記録していた。彼女曰く、ここでは自分のことを人々に見せたり他の人を見る機会を得られるだけでなく、何の仲介もなしに自分の支持者たちと直接関係を築くことができるのだそうだ。
(„Þrír fánar á þúsundkall.“ Bls. 86-87.)
祖母がしてくれた話
ロイガベーグル22番地では色々な話が飛び交っていた。ゲイのいる社会はなにもそこではじめて誕生したわけでなく、昔から多くの話が密かに語られていた。ある晩、若い男の常連客が興奮した様子でバーにやって来て、先週末に祖母から聴いたのだという話をしてくれた。それは、北の方の田舎であった同性愛についての話だった。ある土曜の晩、彼は円卓の騎士のように座る仲間たちにむかって、私に話したときとほぼ一言一句違わずに、再度その話をしてみせた。
――第二次世界大戦が終わってから60年代の間にあったことで、ここからほんの少し郊外にいったところの隣り合う農場に、ふたりの男が住んでいた。彼らがかなり親しいと思われなければ、語られるようなことなんてなかっただろうね、と皮肉な顔をして祖母は言った。
――その人たちは単にゲイだったんじゃないの?と男は笑った。
――今ならたぶんそうやって言うんだろうけどね。でも、私たちはいつも彼らのことを「ソド」って言ってたよ。ふたりとも独り身だったし、なぜだか長続きした家政婦がいなかったこともあって、農場の間でうまく協力しているんだろうって噂だった。家政婦たちは、その農場に幸せな結婚が待っていないことが分かると出ていったんだよ。農場間の密な関係については、彼らが干し草の後ろでかなり親しげに触り合っていたことが証拠だって言われていた。これを疑う余地はまったくなかったし、どうして干し草作りの休憩がこんなに長いのかを知るためだと、双眼鏡を持ち出す近所の人たちに躊躇はなかったね。ふたりの男がそんなにも長く休むなんていつも可怪しく思われていたんだよ。いつだって働き者で手を抜くことなんて滅多にありえないふたりだと知られていたからね。
――誰も何にも言わなかったの?
――言わなかったよ、働き者だし良い人たちだったからね。でも、おそらくそのことのせいで、ふたりが完全に信じてもらえることはなかった。どこからどう見たって立派で影響力のある人物だと評価されても、たとえば地方議会に選出されたことは一度もなかったね、と最後に祖母は言った。
この話は大きな関心を集め、そのまま互いの秘蔵する話を披露する時間となった。それはもちろん、この活気溢れる夜の劇場の一部であった。彼の祖母の話にあるように、当然ゲイ達は以前からそこら中に存在していた。単に彼らは隠されていたのだ。おそらく話の農夫たちは、近所の双眼鏡やそれに付きまとう小市民的思考に十分注意していなかったのだろうが、もしかして彼らは単にまったく気にしておらず、近所の人たちもそうだったのだろうか?
(„Margar góðar sögur amma sagði mér.“ Bls. 62-64.)
期待と絶望の間
多くの男たちは踊るのが好きで、踊る自分たちを見るのが他の人の楽しみになっているのも知っていた。ホールの真ん中あたりにある柱――仕切り壁が取り払われたときに残ったもの――のところが彼らのお気に入りだった。そこからはその場にいる全員からよく見られ、そしてもちろんその場にいる誰もが柱のところの人たちを見ていた。そこは絶望の柱と呼ばれていた。けれども殆どの男たちは柱に大した関心を持っていなかった。わざわざ絶望する必要なんてないことをわかっていたのだ。だが、そこは自分自身の美しさを発揮するのに最も相応しい場所だった。彼らは他の人たちよりも自分の方が抜きん出ていると、白眉であると思っていた。同じように踊れないものたちは、ホールのなかをさまよったあと、同じようには目立つことのない陰の濃い隅の方でじっとしていた。そうして彼らは希望の柱と名付けられた別の柱の辺りでよく待っていた。2本の柱からはその場所を、希望と絶望の間でじりじり動くこの活気溢れる劇場を見渡すことができた。
(„Milli eftirvæntingar og örvæntingar.“ Bls. 38.)
尻抜け
腰抜けならぬ尻抜けについて耳にすることは、今では殆どない。この言葉は「ストゥルトゥルンガ・サーガ」の一場面、富者エイリクルの息子コルスケフグルについての記述で見つけることができる。司教の息子ロフトゥル・ヨウンソンによって、彼は尻抜け男と呼ばれたのだ。こう呼ばれる原因は、ランドスヴェイティン――私の育った古い地区だ――にある木々の活用についての口論にあり、私はそこではじめて件の言葉を目にした。口論では、コルスケフグルがロフトゥルにこう答えた。「司教になったときからお前の父親が立派な人間になったんだとしても、奴が公正だと最初から思っていたやつなんて誰もいなかったし、むしろ自分のことしか頭にないと思われてたんだよ」するとロフトゥルは詰め寄ってきて言った。「おい聞け、お前のような尻抜け野郎が俺の父親を侮辱するかぎり、和解はありえないぞ」
「尻抜け」という言葉は、かつて同性愛者の男性にむかって使われた侮蔑語であり、辞書には古語として説明されている。コルスケフグルは、エイヤフィエトル山の麓にあるストウラダールル谷に住んでおり、非常に裕福ではあったが子どもがいなかった。ハトルヴェイグ・オルムドフティルという名の彼の姪は、コルスケフグルの財産の恩恵にあずかって、後にはスノリ・ストゥルトゥルソンと結婚した。
ゲイは確実に以前からこの国に存在していたのだが、彼らの存在を見つけ出すためには、行間を、直接は語られていないことを読ことが不可欠だ。こうした言葉はニャールのサガの一場面を思い起こさせる。スカルプヒエジン・ニャウルソンがフローシ・ソウルザルソンに青い女用の下穿きを投げつけて怒らせた後にこう言ったのだ。フローシは九夜に一度スヴィーナフェトル山の半妖の花嫁になって、そうして女にされるのだ、と。スカルプヒエジンはフローシが同性愛者だったと仄めかしている。
(„Rassragir menn.“ Bls. 30-31.)